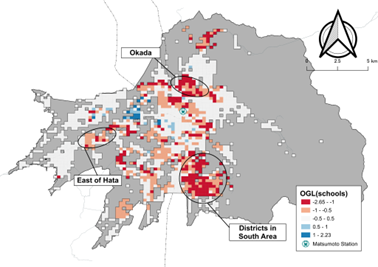工学系研究科都市交通研究室修士2年・佐藤斎
こんにちは。修士2年の佐藤斎(サトウイツキ)です。公共交通による活動機会へのアクセシビリティに関する研究に従事しています。弊研究室のグローバル性をアピールする一環で、こうしてブログを書いています。パスポートすら未取得だったウルトラドメスティックな人間が、やうやうグローバルかつアグレッシブになりゆく弊研究室のもとで、武者修行プログラムに参加し、海外で揉まれていった様子について、体験記を綴っていきます。
ぼんやりとした決心
武者修行プログラムとは、要するに短期留学です。自分で海外の大学の研究室にアポを取り、単身で乗り込んで研究発表を行う、工学部・工学系研究科主催のプログラムです。
近年、弊研究室では多国籍化が進んでおり、英語はもはや必須言語となりました(ちなみに、2025年4月現在で日本人と留学生がほぼ同数になりました)。国内ではなんだかんだで日本語が使えてしまうため、いやおうなしに英語を使う環境をうっすらと求めていたのですが、続けざまに日本人の同期が海外に挑戦している様子も目にして、焦燥半分欲求半分、海外へのぼんやりとした冒険心が芽生えました。
幸いなことに(?)自分の研究分野には英語の文献が多く、肝心の受け入れ先に関しても、研究に使用していたツールのエンジニアであるAnson Stewart先生をGian先生が紹介してくださったため、外堀は着実に埋まっていきました。急かされるままに書類を提出し、とうとうアメリカ合衆国はマサチューセッツ工科大学(MIT)、Urban Mobility Labへの武者修行が内定しました。TOEFLスコア80点未満の自分に、果たして英語で研究の議論ができるのでしょうか。不安を抱えながら渡米を迎えました。
現地 ―ビビり―
修行は2025年2月17日〜3月8日の約3週間で、Boston近郊のCambridge市中心部に滞在しました。成田からChicagoを経由してBostonへ向かいましたが、現地は-10℃近くまで冷え込み、いささか鼻が凍りました。調べてみたら、大体札幌でした。
リスニングがやや苦手だったので、渡航前からニュースやポッドキャストを聴きまくり、機内でもダウンロードした番組を繰り返していたのですが、効果はあったのでしょうか。英語での食事の注文すら初めてで、本当に飢え死にするのではないかという危機感から、とにかく必死に英語を使いました。「ネイティブはテイクアウトのことを“to go”って言うのか!?」レベルのコロケーションにすら悩みましたが、近くのアジア系スーパーや親切なAirbnbのホストのおかげで、かろうじて生活が成り立ちました。
滞在2日目には、大学でAnson先生と初めて対面しました。椅子ではなく机に腰掛けようとしたほどにはガチガチに緊張していましたが、研究に関する議論を重ねるうちに、少しずつ英語が出るようになりました。文法や発音云々よりも、まず話そうとする積極性を見せることが大切で、夕食ではお互いの趣味の鉄道について、話が盛り上がりました。Massachusetts州では飲酒が21歳から合法と日本より若干厳しく、パスポートの提示を求められましたが、店員が私の年齢を計算できずにアタフタしていた姿が印象に残っています。
現地 ―And then―
先方からリクエストされた課題は、自身のアクセシビリティ研究と、時刻表や運賃などのバス情報を格納するGTFSデータの、日本における進展をまとめたプレゼンでした。事前にAnson先生とのミーティングや、研究室で出会った学生との議論を通じて、2週間かけて自分のプレゼンをブラッシュアップしてゆき、学生や教授が約30名集まるセミナーでの発表に臨みました。みんな興味がなくてお通夜ムードだったらどうしようという心配をよそに、25分間の発表を終えるやいなや、海外と比較した日本のデータの優位性や、評価する施設の是非、さらには今後の研究の方向性に関する議論など、実に様々な観点から質問をいただきました。努力の甲斐あり、おおよそは答えることができましたが、真意を掴めずに打ち返してしまった質問もあり、自分の理解に落とし込むために、パラフレーズなどの工夫を施す必要性を痛感しました。とはいえ、日本語を一切使わない研究発表は今回が初めてで、今回の滞在で最も大きな目標を達成することができました。
さて、峠を越えてしまえば、後は観光あるのみです。Bostonといえば茶会事件や美術館が有名ですが、私にとっては趣味の鉄道をおいてほかにありません。Bostonの地下鉄(The T)はアメリカ最古で、地下鉄に直通する路面電車や、パンタグラフと第三軌条を併用した車両など、日本ではお目にかかれない鉄道のオンパレードでした。Mattapan地区を走る1940年代製造の古い路面電車にも乗車し、The Tの全区間完乗を達成できました。特にMattapan地区は治安の悪い地域という噂を耳にしていたので、学生や先生方、さらには現地の駅員や警察の方々にも話を伺い、注意して挑みました。たった3週間の滞在ではありましたが、最後には英語で生活を楽しめるようになりました。
修行を終えて
初めての海外滞在を乗り越えることで、だらけた暮らし方を見つめ直すことができました。自分の中で、常識を超えて半ば信仰と化していた日本の価値観を相対化し、視野を広げることにも繋がりました。面倒くさがりで食わず嫌いな私の性格も、少し克服できたように思います。なにより、元々の英語力よりも、できるだけ多くを伝えて多くを理解しようとする積極的な姿勢と、根拠をはっきりと示せる論理的な思考に価値があると実感しました。不安ばかりに気を取られず、とりあえず一歩を踏み出してみる勇気は、間違いなく弊研究室の環境で育まれたものです。今後も国際学会での発表を控えていますが、学術の交流のみならず、普段の生活でも積極性を忘れずに、挑戦を続けていく所存です。
Massive shout-out to Dr Anson Stewart and all the members of the Urban Mobility Lab at MIT!
おかねのはなし:
費用は食費交際費全て込みで約65万円でした。飛行機代が往復33万円、宿泊代が20万円、雑費が約12万円となりました。武者修行の補助を差し引くと、20万円は自弁になりました。食費を節約すべく、インスタント味噌汁を持ち込んだ自分は天才です。